2025.02.17
乗れば乗るほど元気になる?脳科学やAIでひとの本質を研究するマツダのクルマづくりとウェルビーイング
マツダは単なる移動手段としてのクルマを超え、「乗れば乗るほど元気になるクルマ」の開発に挑戦しています。その根底には、マツダがずっと追求してきた「ひと中心」の哲学と、移動がもたらすウェルビーイングへの探求がありました。「移動は、私たちの人生をどう豊かにできるだろうか?」
今回MAZDA MIRAI BASE編集部は、その研究の最前線について、マツダ技術研究所 次世代人間中心システム開発部門 統括研究長の本田正徳、上席研究員の道田奈々江に話を伺いました。
「乗れば乗るほど元気になるクルマ」とは?人間研究とクルマの関係
本田:
次世代人間中心システム研究部門では人間研究、AI、量子コンピュータ、クルマそのものなど、さまざまな専門家が一緒になって「ひと中心」の新しい価値を生み出すことを目標に研究をしています。マツダは「乗れば乗るほど元気になるクルマ」の研究も行っていて、その領域での研究リーダーが道田です。


クルマに乗ることで、歩かなくなり不健康になってしまうイメージもあったかと思います。「乗れば乗るほど元気になるクルマ」とはどんなものなのでしょう?
本田:
じつは「ウェルビーイングには『移動』という体験が重要である」という先行研究が数多くあり、クルマはそこに大きく寄与できる可能性がある、とマツダは考えているんですね。
道田:
歩く代わりにクルマに乗りましょう、と言っているわけではないんです。運転そのものを楽しんだり、ドライブ中に風景や自然の空気を楽しんだり、出かけた先で新しい味や、新しい人と出会ったりするなど、移動を通じてさまざまなポジティブ体験をすることが、心と身体を活性化すること、元気につながる、と考えています。
マツダでは、こうした移動にともなうさまざまな刺激、周囲の音の変化、自然界の空気の匂い、運転にまつわる手足の動きなどの感覚、そして移動した先での誰かとの出会いに対して脳が情報処理を行い、ポジティブな感情を体験する ことが、ウェルビーイングにつながるのではないか、と考えています。


「脳」が重要なキーワードになっているんですね。現在、道田さんはどんな研究をしているのでしょうか?
道田:
マツダはもともと「負担がない」「楽に運転できる」「安全にクルマに乗れる」といったことをベースに人間工学 *¹を研究してきました。さらには、「きびきび感」「リラックス感」「ワクワク感」といった「◯◯感」という人間の主観に着目し、それを工学的な指標と結びつけていく「感性工学」の知見を積み重ねてきています。
私たちは、それらの「◯◯感」だけでなく無意識の反応まで対象とし、脳科学の知見を活かした「感性脳科学」という領域に踏み込んで研究しています。
*¹人間が自然に動けるように、安全で使いやすいモノや環境を設計しデザインに活かす技術。
ひとの「感性」に注目するマツダの研究
感性脳科学とは、どのような研究なのでしょうか?
道田:
感性脳科学では、「〇〇な気がする」といった人間の感覚の原因を明らかにし、それをクルマの開発やサービスに活かすということをやっています。
例えば、フロントウィンドウの形についての事例ですが、流線型のクルマが流行った時期には「昔のクルマのほうが運転しやすかった“気がする”」と感じる人も少なくありませんでした。この感覚に注目するきっかけとなったのは、『昔の車は、窓枠越しの風景が美しかった』という引退したエキスパートの何気ない一言でした。
なぜ窓枠越しに見た景色に、クルマによって違いがあるのか?
マツダの研究チームはこの感覚の正体を探るため、フロントウィンドウの窓枠の形に着目。流線型フロントウィンドウデザインでは窓を支える柱が傾くことで、窓枠が逆台形のような形に見えることに気づきました。
そして脳の情報処理メカニズムに基づき、目立つ部分を計算・表示する技術「サリエンシーマップ」を使い、窓の形状によってドライバーの注意が思わぬ方向に引きつけられることを解明。さらにfMRI*¹やドライビングシミュレータを用いた実験により、窓枠の形状がドライバーの距離感や運転の安定性、注意の振り分けに影響を与えることが確認できたため、ドライバーが進行方向に視線を安定させたうえで、見るべきものに注意を向けやすくなるよう、マツダではフロントウィンドウデザインの設計に気をつかっています。このように得られた発見は、マツダCX-8以降の運転のしやすさと美しいデザインを両立する設計に活かされています。
*¹:fMRIとは:参照ページをご覧ください






感性工学、感性脳科学は自動車メーカーの研究としてはユニークに感じますが、道田さんがこういった研究に取り組むようになったのはなぜだったのでしょうか?
道田:
もともと私は広島大学の総合科学部で精神生理学を学んでいました。精神生理学とは、心と身体の相互作用を生理指標を活用して明らかにする学問です。たまたま大学院時代の研究室にマツダの方が来て、一緒に実験などをするうちにマツダに誘ってもらい、入社に至りました。その後、「心」と「体」のつながりをメインに、人間の骨や筋肉の仕組みに合わせた、心地よいと感じるクルマのシート開発に携わっていました。
その当時から「人間と接する部分」の研究をしていたんですね。
道田:
シートの開発をしていた当時から、「◯◯感」をよくしていくために脳科学を研究する必要性を感じていました。その後は、文部科学省の「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」の枠組みのもとで、広島大学や生理学研究所などの脳科学研究者のみなさんと知覚や感性を可視化し、社会実装につなげる研究共同を進めていきました。
たとえば、クルマの運転で単にまっすぐ走るよりも、スラローム(等間隔に設置された障害物を左右交互にかわし進路転換を行うこと)を走るほうがワクワクする人が多いとしたときに、ドライバーに脳波計をつけてもらい、その「ワクワク感」を感じるときに活性化する脳の部位の状態を計測する実験を行いました。ほかにもクルマのインテリアの質感の感じ方や、運転席と助手席に二人で乗っているときの共有感を定量化する、という試みもありましたね。


本田:
私が統括している「次世代人間中心システム研究部門」では、AI研究も長年進めてきました。これまでAI活用というと、車両のCO2排出量削減を目指したクルマの軽量化開発などが主でしたが、マツダが大切にしている「ひと中心」の視点で新しいお客さま価値を創造したいという想いで、現在はAIによって人間の特性や状態を予測するモデルをつくることにも挑戦しています。


「移動」で元気や歓びを感じられる「基盤力」を積み重ねる
「ひと中心のクルマづくり」で、お二人が現在イメージしているのはどんなことなのでしょうか。
道田:
私が大切だと考えているのは「感情体験」と「成長」です。ポジティブ感情を多く経験するほど幸福度が上がりますが、一方で幸福度が高い人はポジティブ感情を感じやすいというように、経験を積み重ねた状態と経験時の感情は相互に関連していることは、脳科学的にも明らかにされています。
そもそも出かけるのが面倒くさい人でも、「友達に誘われて出かけていったらすごく楽しかった」ということはよくありますよね。「自分が行動したから、楽しい体験ができた」とか「難しいと思っていたことができた」ということが、次の機会にまたアクションを起こす力になります。良い結果を予測してアクションを起こすことで、またポジティブな体験を重ねることができる、この前向きに生きる力のことを私は「基盤力」と呼んでいて、成長させることができると考えています。
単に自動運転で目的地まで連れていってもらうというより、たとえば「外出」という行動のための主体性の発揮をサポートするイメージなのでしょうか。
道田:
そうですね、「知らないあいだにできた」ではなく、「自分でできた」喜びを感じられることが基盤力の成長をともなう幸福感につながります。各人の運転技術に合わせたサポートをして、マツダ車とのかかわりのなかで少しずつ前向きさを獲得していってもらう、そういうものをイメージしていますね。


たとえば免許取り立ての方が、運転が上手くなるようにサポートするだけではなく、「そろそろ免許を返納しなければいけないかもしれない」と不安を感じているご高齢の方なども想定されているのでしょうか。
本田:
はい。たとえば、反射神経や、空間を把握する力、状況を判断する力などに不安を感じはじめていて、「初めての場所にドライブして、新しい体験をしてみたいけど、ちょっと自信がない」という方に、「自分の力でまだまだ新しい世界を切り開いていけるんだ」と思ってもらえることも、広い意味では「成長」だととらえられますよね。
道田:
「ちょっと身体が弱ってきたかな」と感じる方って、出かけなくなって体力が落ちて、さらに人とのコミュニケーションが少なくなると、認知能力も落ちていってしまうという負のループに入ってしまいがちです。逆に行ったことのない場所にクルマで出かけ、外を歩いたりすることもトレーニングになる。「移動」によって心身の力を取り戻す、そのサポートをクルマが行うというイメージです。


脳科学で迫る、移動体験の驚くべき効果
クルマに乗る人の体力や運転技術によって、サポートをする事柄や度合いがかなり変わってきそうですね。
道田:
はい。「乗れば乗るほど元気になるクルマ」のためには、それぞれの人の状態を推定して、その人に適した働きかけをすることが必要です。そこでいま、マツダは文部科学省の「共創の場形成支援プログラム(COI NEXT)」の弘前大学拠点に参画し、青森県にある弘前大学との共同研究を進めています。
弘前大学では20年前から「岩木健康増進プロジェクト健診」といって、1,000人以上の健康な人の心身データを3,000項目で調査しデータ化するプロジェクトが行われてきました。私たちはそこで得られたデータをもとに人の健康と幸福、ウェルビーイングとクルマの関係性を明らかにしようとしています。病気や怪我をした人のデータは病院でたくさん取ることができますが、じつは健康な人のデータは意外に少ないんです。弘前のデータは大規模かつ長期間にわたるので、非常に貴重なんですね。


道田:
面白いのは、「クルマが好きな人は男女ともに健康であることが多い」ということがわかってきたことです。移動が好きで、自然の景色にワクワクすることが認知機能の高さなど健康度の高さにつながっていて、それはもしかしたら「感性の豊かさ」につながっている。感性が豊かな人は健康で幸福である可能性が高いですよね。
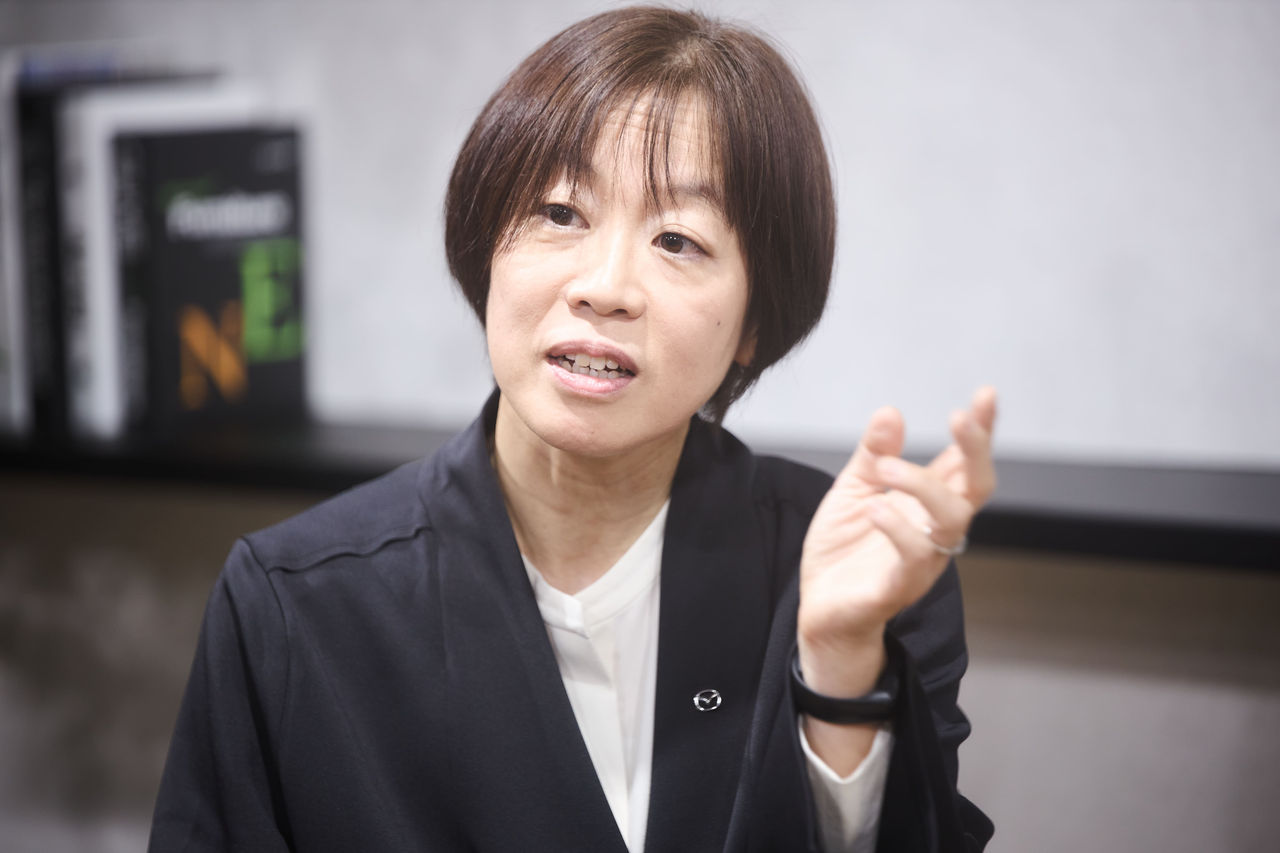
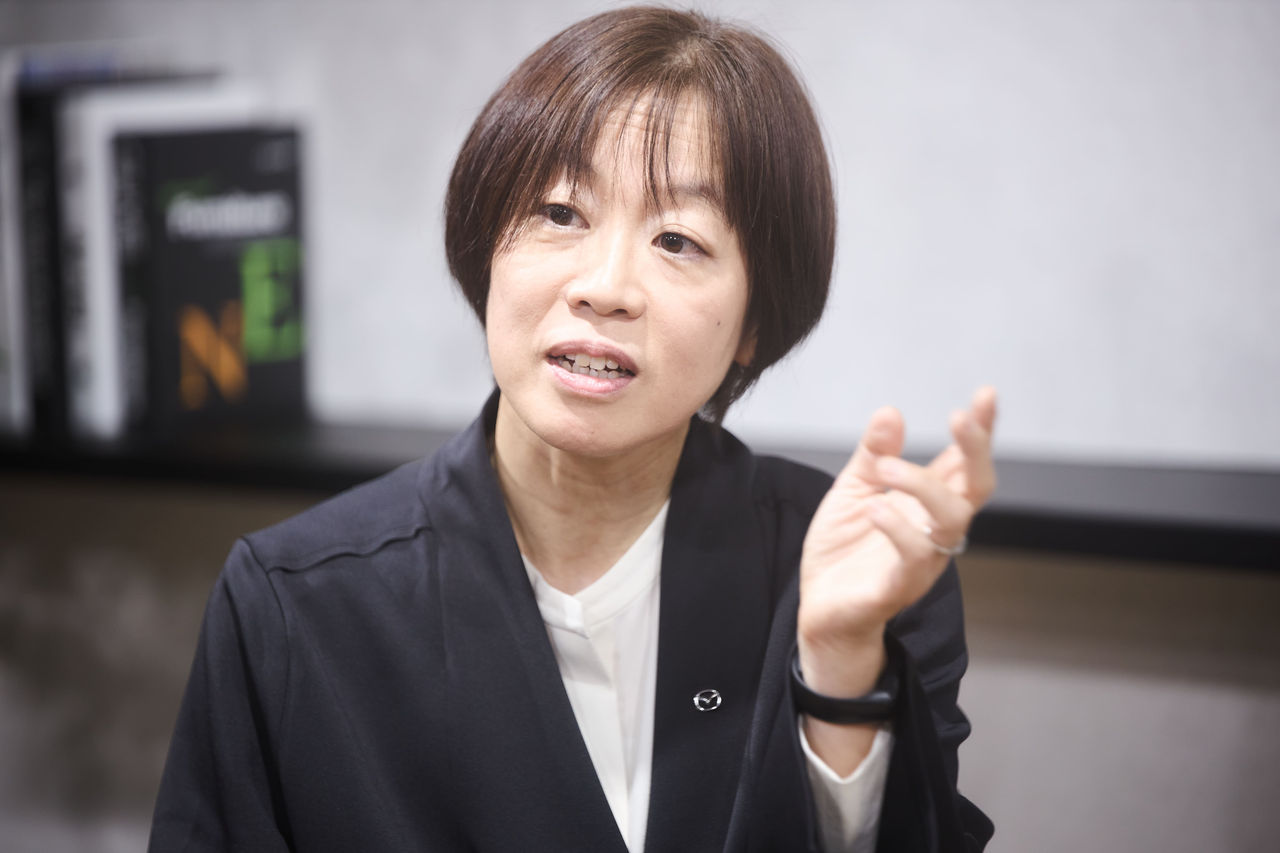
マツダの研究は人間の感性にまで及んでいますが、お二人の研究に対するモチベーションはどのようにして生まれているのでしょうか。
道田:
私が心理学をやりはじめたのは、「自分と違う人が、なぜ違うのかを知りたい」と思っていたからです。結局、人をわかることで、自分のことをわかり、自分がなぜそう感じるのか、知りたかったのだと思います。ウェルビーイングはまさに「善(よ)く生きる」ということだと思いますが、私は学生時代から「ひとが善く生きるって何なんだろう?」ということに興味をもって生きてきたので、それが根源的なモチベーションになっていると思います。
本田:
私の場合、古くは山本健一さんが提唱された「感性工学」など、マツダの人間研究の長い歴史で育まれた資産や風土と、現代の極めて激しいAIやIT技術の進化を融合させて、次の時代のひと中心の技術をつくっておかないといけないという責任感が大きいですね。マツダは自動車メーカーとしてはそこまで大きくない会社だからこそ、自由な発想で研究に取り組むことができます。そういう「自分の力で世界を広げていける」ということを楽しんでいる感覚がありますね。
感性脳科学研究はこれから社会実装へと向かっていくと思いますが、お二人の今後の展望はいかがですか。
道田:
もともとマツダの開発は、各自が「ウェルビーイング」という言葉を明確に意識していない時代から、それに近い発想をもって研究開発にあたっていたと思います。さきほど「自分が行動したから、難しいと思っていたことができた」「自分の力で世界を切り開いていける」という実感が大事だという話をしましたが、自動車メーカーであるマツダでは移動体験を通じてそれを社会に届けていきたいと考えます。
マツダは部門間の壁も薄く、いろんな人の力を借りてみんなで一緒にクルマをつくっていける感覚があります。さらに今は社内だけではなく、弘前大学での取り組みのようにさまざまな企業の方たちとともに研究を進めていける環境ができています。他の人とつながる範囲をどんどん広げながら、これからも研究を進めていきたいですね。
本田:
私は、マツダが今まで培ってきた人間研究の知見を、AIやビッグデータの活用を通してできるだけ早く社会に届けたいですね。そしてもうひとつ、これまでマツダの強みとしてモデルベース開発(コンピュータ上でシミュレーションを行うモデルを作成し、開発と検証を同時並行で行う手法)がありましたが、それをひと中心の研究で生み出す人間モデルと組み合わせ、世界一の強みにしていきたいです。それらを通じて、お客様や社会のウェルビーイングにつなげたいと考えています。


編集後記
「乗れば乗るほど元気になるクルマ」。今回の取材で、その言葉の背景にある想いや挑戦に触れ、マツダの研究が人々の移動の歓びとウェルビーイングにつながっていくという新しい可能性に気づかされました。人の感覚や感性を解き明かそうとする研究。そして「基盤力」という考え方 – 小さな成功体験の積み重ねが、人を前向きにする力になっていく。その根底には、長年追求してきた「ひと中心」の思想が受け継がれていました。次回は、「乗れば乗るほど元気になるクルマ」の社会実装に向けて、青森県弘前大学との共同研究に従事するマツダの仲間を訪問、その研究現場からレポートをお届けします。ご期待ください!








