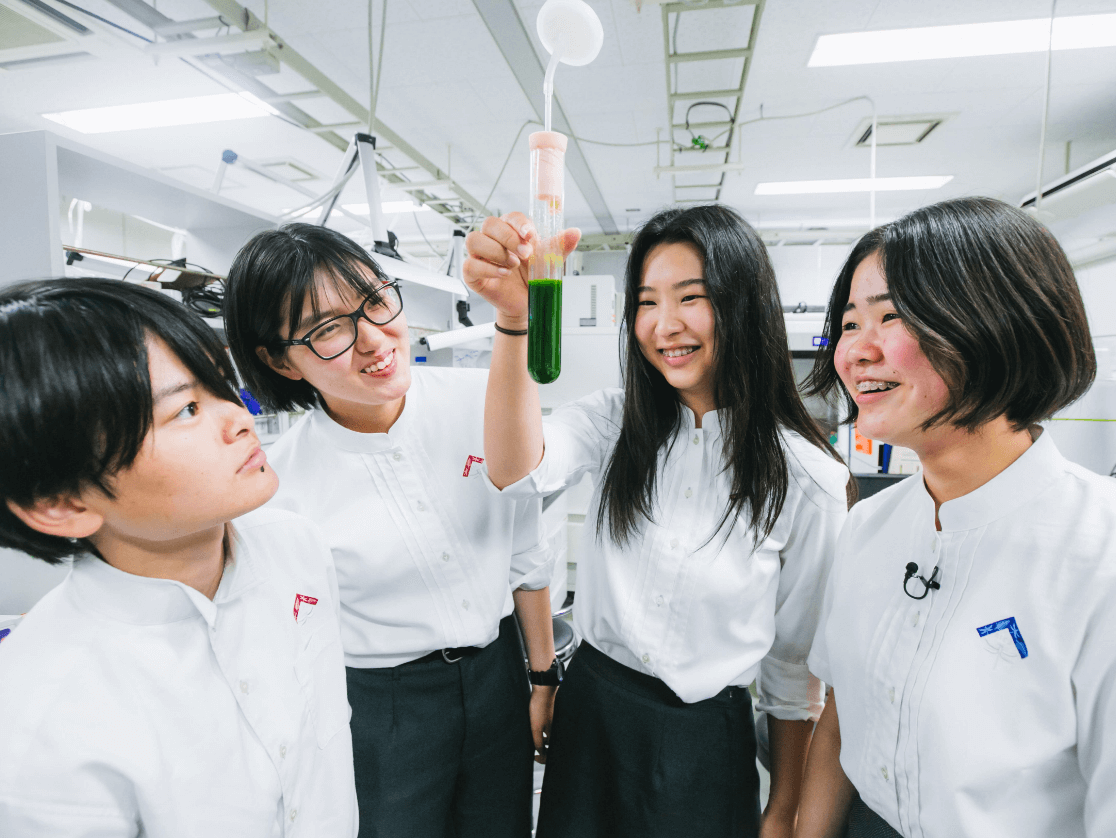2024.10.31
未来への不安は解消された?マツダを見学した高校生が語るリアル
2日間にわたる見学ツアーで、マツダのさまざまな取り組みを知った高校生たち。広島大学とマツダが取り組む、微細藻類を活用した次世代バイオ燃料実用化に向けた研究。新しい技術や工場での小さな改善の積み重ねなどにより、CO₂削減にチャレンジするサステナブルなクルマづくり。MAZDA ICONIC SPに、広島が頭を抱える廃棄された牡蠣殻を生まれ変わらせたデザイナーの想い……。今回の見学を経て、マツダに対する印象はどのように変化したのでしょうか? そして、その経験が4人の心に残したものとは? 高校生たちに、率直な思いを聞きました。
広島のAICJ高校に通う4人。左から入江さん、橋本さん、高橋さん、田辺さん。
環境を破壊することなく、カッコいいクルマを心から楽しめる時代が来てほしい
今回は2日間にわたり、マツダのサステナブルにまつわるさまざまな取り組みを見ていただきました。まずは、それぞれ印象に残ったことや感じたことを教えてください。
入江:
私は微細藻類の研究が印象に残りました。もともとバイオ燃料に関心があって見学前から気になっていたのですが、広島大学やマツダの工場内など、実際に研究が行なわれている場で微細藻類からエネルギーをつくり出しているところを見ることができて、ますます興味が湧いてきましたね。


入江さん
橋本:
私も入江さんと同じく微細藻類の研究については興味があったので、実際に使われている装置なども見学しながら培養の方法を学ぶ機会をいただけたのがありがたかったです。
広島大学とマツダの工場内での研究の違いや、量産化する際に研究室と同じ精度を出すのがいかに難しいかなど、興味深いことばかりでした。理想と現実の違いというか、研究室ではうまくいってもそれを実用するとなると、また別の課題が出てくるということがリアルに感じられて、とてもいい経験になったと思います。


マツダの工場敷地内に設けられた微細藻類を培養する水槽。広島大学と連携しながら微細藻類由来のバイオ燃料の研究開発を進め、石油由来のガソリンや軽油などに代わるクリーンエネルギーの実用化を目指している。


橋本さん
橋本:
それから全体的な印象として、今回出会った大人たちはみんな、すごく生き生きしているなって。正直、仕事ってすごく大変で、しんどい思いをしながら働いている大人が多いイメージだったんですけど、マツダに関わる人たちはどこか楽しそうで、自分の仕事に信念を持って向き合っているように感じました。
田辺:
特に印象に残ったのは、自動車の組立作業です。工場で導入されているさまざまな「からくり改善」の工夫に、とても興味を惹かれました。


塗装された車体にパーツを組み合わせ、完成品にしていく様子を見学。


工場内で働く人たちが自ら考案した「からくり改善」。作業を無駄なく安全に行なうための工夫が随所で見られた。
田辺:
微細藻類から燃料をつくる壮大な研究を行なっている一方で、工場内のからくり改善みたいに小さな工夫を一つずつ積み重ねて、少しでも省エネにつなげようとしていることに驚きました。私たちも少し考えて工夫すれば、できることがじつはたくさんあるのかなと思いましたね。
それから、今回のツアーを通じてマツダや自動車に対する見方も大きく変わりました。正直、これまではあまりクルマに興味がなくて。むしろ、環境に良くない乗り物という印象を抱いていたんです。でも、今回マツダのいろんな取り組みを知って、今はこんなに環境のことを考えてクルマをつくっているんだなって。


田辺さん


高橋:
私もいろんなことを感じたんですけど、まずはマツダって楽しそうな企業だなというのが一番の感想です。もともとマツダのクルマや会社自体が好きで、たとえばクルマのデザイン一つとってもシルエットを見ただけでマツダだとわかる、いい意味でクセのあるスタイルに魅力を感じていました。
それができるのは、マツダならではのチャレンジのしやすさだったり、やりたいことをやらせてもらえる風土みたいなものがあるからなのかなと、今回の見学を通じて感じました。
高橋さんは、初日に訪れたマツダミュージアムに展示された歴代のマツダ車を見ているときも、かなり興奮されていましたよね。本当に好きなんだなと。
高橋:
もともと乗り物全般が好きで、なかでもスリルを感じるものに惹かれます。自動車ならオープンカーみたいに、自分がさらけ出されているような感じっていうんですかね。だからマツダのロードスターとかも好きだし、将来はMAZDA ICONIC SPのようなクルマにも乗ってみたいと思っていて。


2023年に「ジャパンモビリティショー2023」で公開されたコンパクトスポーツカーコンセプト「MAZDA ICONIC SP」(マツダ アイコニック エスピー)。搭載バッテリーを再生可能エネルギー由来の電力で充電することで、実質カーボンニュートラル燃料での走行が可能となる。
高橋:
ただ、実際に自分が免許を取ってクルマを買えるようになるのは、早くても数年先です。そのときに、いまのままだと気兼ねなくスポーツカーを楽しめなくなるんじゃないかという不安な気持ちもありました。
ヨーロッパを中心に海外では電気自動車にシフトする流れもあるし、ますます環境への影響が問題視されていくなかで、自分は将来、本当にマツダのクルマに乗れるんだろうかって。そういう意味では、今回見学したマツダの環境への取り組みが身を結んで、環境を破壊することなくカッコいいクルマの運転を心から楽しめる時代が来てほしいなと思います。


マツダミュージアムでは環境に配慮した車づくりを学ぶとともに、歴代のマツダ車も見学。
「正直に言うと、マツダの環境への姿勢は少し遅れている印象がありました」
みなさんはそれぞれ、現在や未来の地球環境に対して不安と問題意識を抱えていると思いますが、今回、マツダのサステナブルな取り組みを知って、心境に変化はありましたか?
高橋:
私はむしろ、より不安が強くなりました。というのも、企業の生産活動が環境に与える影響って、自分が想像していたよりもずっと大きいんだなって。たとえば自動車ひとつとっても、走行中に温室効果ガスを排出するというだけでなく、クルマを生産するときにもたくさんのエネルギーを使い、多くのCO₂を出している。マツダだけでなく、他社や他国でも同様に自動車が大量生産されていて、なかには環境よりも利益を追求する会社もあるだろうし……。そう考えると、やはり不安で。


高橋:
正直に言うとマツダに対しても、環境への姿勢は少し遅れている印象がありました。マツダのクルマってデザインがかっこいいから、普通に売れるじゃないですか。わざわざコストをかけて環境やエネルギーに取り組む理由がないのかなと思っていて。
だから、こんなにマツダがいろんな取り組みをしていたことに対しては、驚いた部分もあります。微細藻類の研究だったり、マツダ社内にある発電所のエネルギー源を石炭からアンモニアに変えようとしていたり、ここ数年で迅速かつ大胆にシフトしてきていることもわかって、ここから一気に加速していくのかなとも感じました。
橋本:
私も見学前は、マツダはどうしてあまり電気自動車に力を入れていないのか不思議に思っていました。ただ、今回マツダの方から電気自動車のバッテリーをつくる際に、そもそも多くのCO2を排出してしまうと聞いて納得しました。あえて電気自動車にシフトせず、LCA(ライフサイクルアセスメント)を採用したり、バイオ燃料にフォーカスしたりといったマツダのアプローチは、じつはすごく理にかなっているのかなと思います。


マツダが考えるLCAの全体像


マツダの工場敷地内にある火力発電所。工場で使う電力の大部分を自給自足で賄っている。今後は燃やしても二酸化炭素を排出しないアンモニアなどの燃料を使った発電所を新たに建設する予定。
入江さんは微細藻類の研究に触れて、よりバイオエネルギーへの興味が増したと。
入江:
はい。今回、初めて研究の現場を見て、エネルギーをつくり出す仕組みを知って、自分もそういう道に進みたいという気持ちがいっそう強くなりました。微細藻類も面白いと感じましたが、もっといろんなエネルギーについても学んだうえで、将来の選択肢を増やしていけたらと思っています。


「きっかけさえあればクルマに興味を持つ人も増えると思う」高校生たちがマツダに望むこと
みなさんは、これからのマツダはどうなってほしいと思いますか?
田辺:
一つ思ったのは、若い人が自動車を好きになるような働きかけをしてくれるといいのかなって。今回のツアーを通じて私がワクワクしたように、きっかけさえあればクルマに興味を持つ人も増えると思うので。
特に私たちの年代はまだ免許も取れないし、クルマや運転ってすごく遠いものに感じられます。だからこそ、マツダにとって直接的なターゲットではない10代に向けて、企業の取り組みを知ったり、いろんな自動車を見学できたりする機会をつくってくれたら嬉しいですね。


塗装工場での一コマ。
橋本:
先ほども少し話しましたが、世の中全体で電気自動車へシフトしていく流れもあるなかで、マツダはもう少し先の未来を見据えて微細藻類などのバイオエネルギーに注力していると思います。自動車メーカーとしては珍しい取り組みだと聞きましたし、本当に新しいクリーンエネルギーを開発することができたらマツダがその分野の先駆者になれると思うので、このまま頑張ってほしいです。
入江:
私がマツダにお願いしたいのは、みんなが何も気にせず、安心してクルマの運転を楽しめる世の中をつくってほしいということ。
さっき高橋さんも言っていましたけど、せっかく運転するなら地球温暖化のことを考えずに楽しみたいですよね。でも、いまはどうしてもそのことが頭をよぎってしまう。だから、マツダにはこのままクリーンな製造方法を追求したり、バイオ燃料の研究を進めたりしてもらって、私も将来はカーボンニュートラルなマツダ車に乗りたいなと思います。


では、最後にみなさんにお聞きします。今回の経験は、自分の将来に生きると思いますか?
入江:
私は環境問題に関心を持っていますが、いまの段階では将来の道を限定せずに、いろいろなものを見て学びたいと思っています。今回、クルマの製造過程での省エネにつながる工夫だったり、バイオ燃料だったり、アンモニアを使った新しい発電方法だったり、さまざまな分野の新しい知識を得られたので、自分が将来何をしたいのか考えるうえでも大きな2日間でした。
橋本:
私はまだ将来やりたいことが具体的に決まっているわけじゃないけど、大学では経営を学ぶつもりです。今回は2日間だけでしたが、経営の際に大事なことをたくさん学べた気がして、すごく有意義な時間でした。
たとえば、社員の方の働きやすさだったり、産学連携だったり、環境問題への取り組み方だったり、それってすべて会社の経営方針にも関わる部分だと思うんです。将来のことはわからないけど、もし自分が起業したり、どこかの会社の経営に関わったりすることがあったら、今回の経験が大きな糧になるんじゃないかと思います。
田辺:
マツダは自動車をつくっている会社ですが、この2日間で見てきた取り組みには自動車の専門家だけでなく、いろんな分野の専門家が関わっていることを知りました。それは大きな発見でしたね。
私は将来、建築の仕事をしたいのですが、自分が好きな分野や得意なスキルを活かす道は一つじゃないんだなって。建築士にならなくても、建築の知識を生かせる仕事の関わり方はたくさんあると思えたので、将来の選択肢が広がった気がします。
高橋:
今回改めてマツダのことを知って、日本では珍しいくらいクリエイティブで面白い企業だなと感じました。いまは世界情勢も不安定だし、自社の利益だけを追求する会社もあるなかで環境に配慮しながら戦っていくのは大変だけど、マツダなら生き残っていけそうだなと思いました。自分がしっかり勉強して立派な大人になったら雇ってほしいです。


和やかな雰囲気のなか座談会は終了。マツダとしても高い環境意識と未来への視座を持つ高校生との交流で、大きな刺激を得ることができました。
編集後記
振り返れば、今回の企画は、2024年2月のサステナブル・ブランド国際会議に端を発します。イベント後、入江さんからマツダに見学依頼のメールをいただき、今回のサステナブルツアーを実現することができました。地球環境への問題意識を通して、新しいつながりが生まれたことは、私たちにとっても大きな発見でした。
この度、MAZDA MIRAI BASE 編集部が産声を上げ、前向きな未来に向けたストーリーを、読者の皆さまにお届けできることを嬉しく思います。マツダがつくりたいのは、誰もが、いつまでも、ワクワクする移動体験の歓びを感じることのできる未来。今回見学してくれた高校生の皆さんのように、今後もマツダが目指す未来に共感していただける仲間たちと垣根を越えてつながり、一つひとつ挑戦を続けていきます。今後の活動もお楽しみに!


2日間案内を務めた経営戦略本部の河崎豊と。