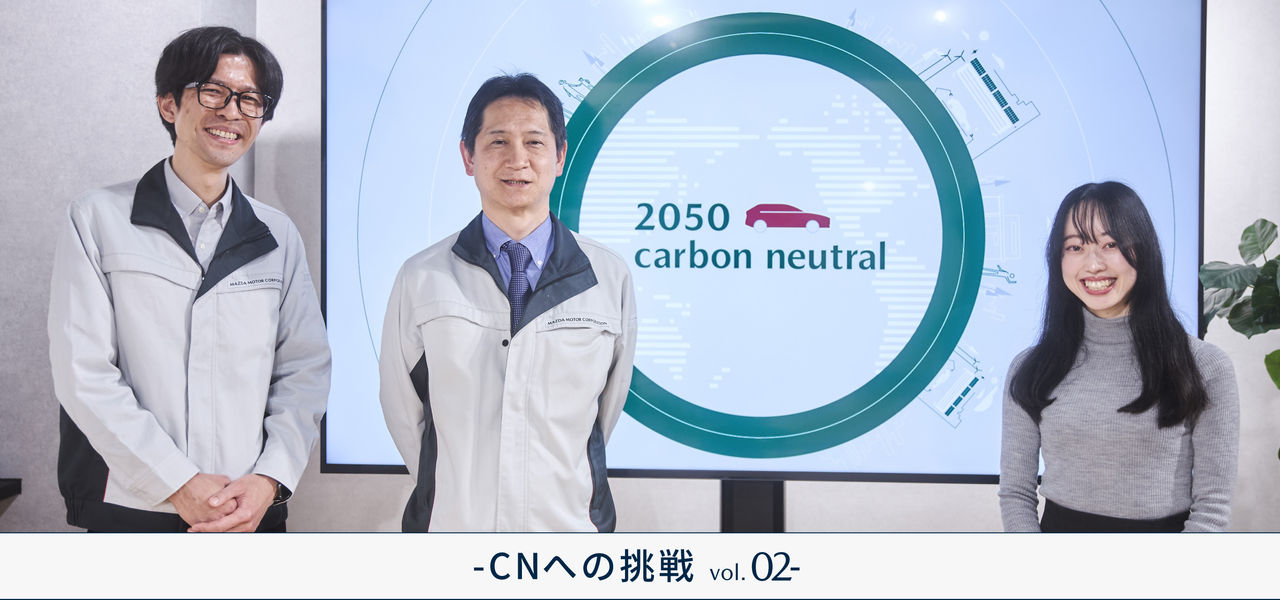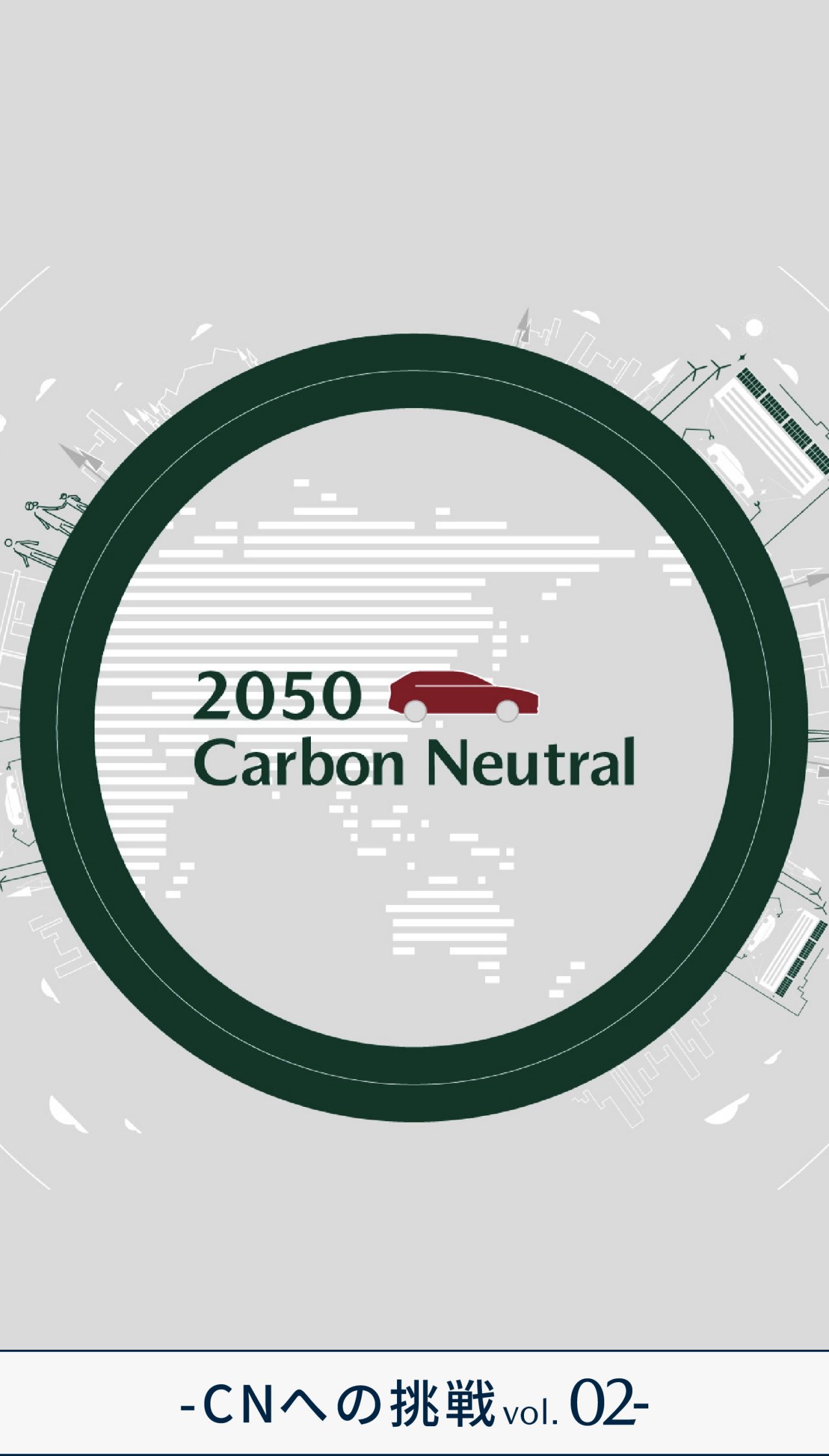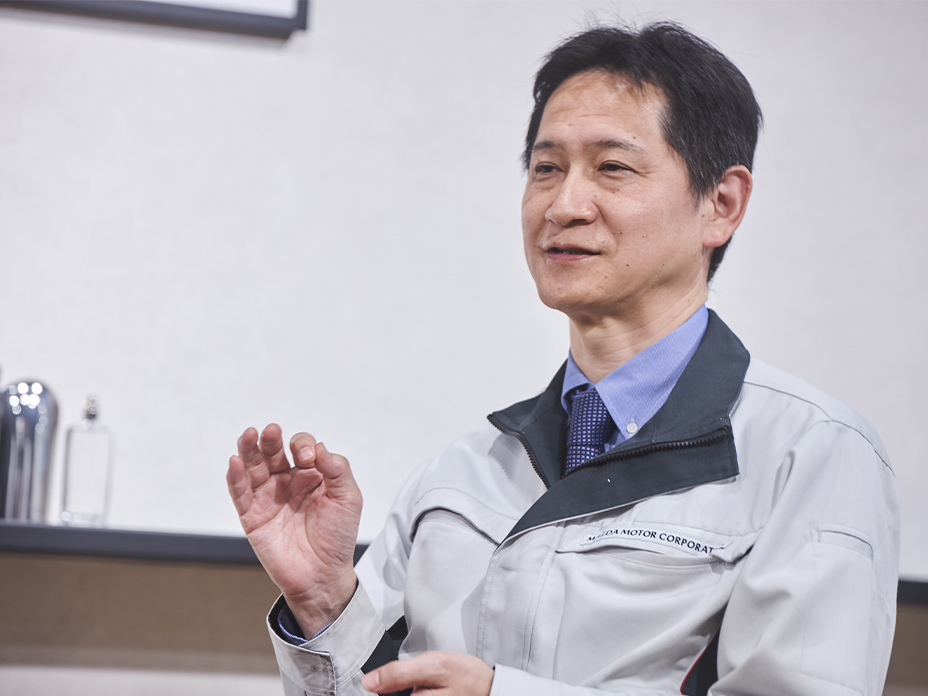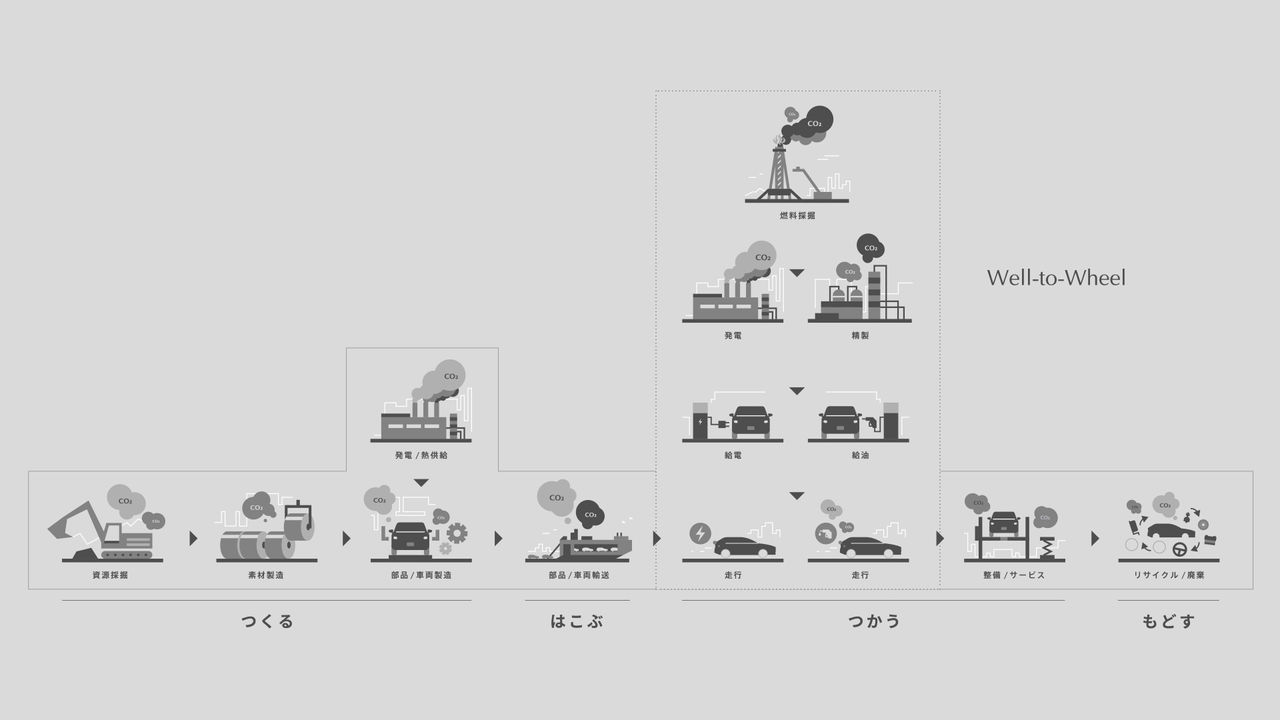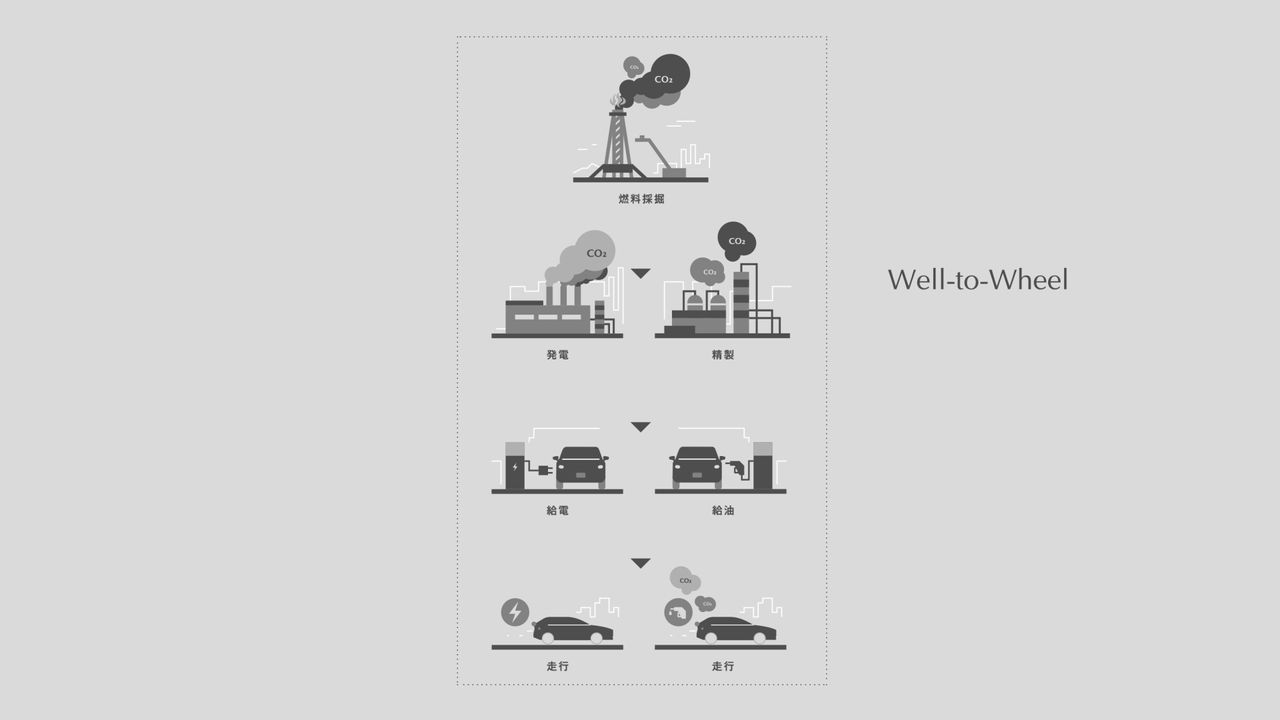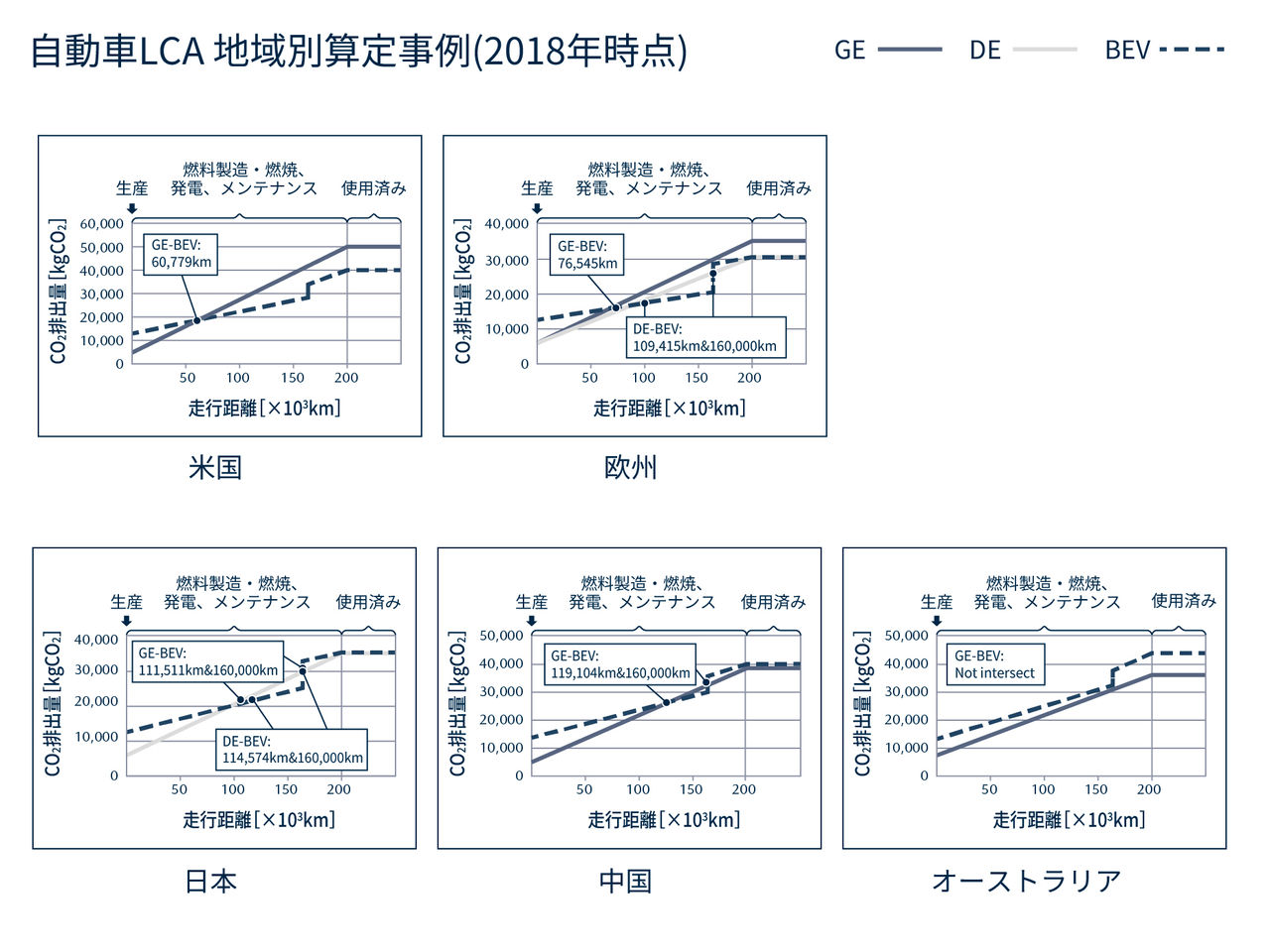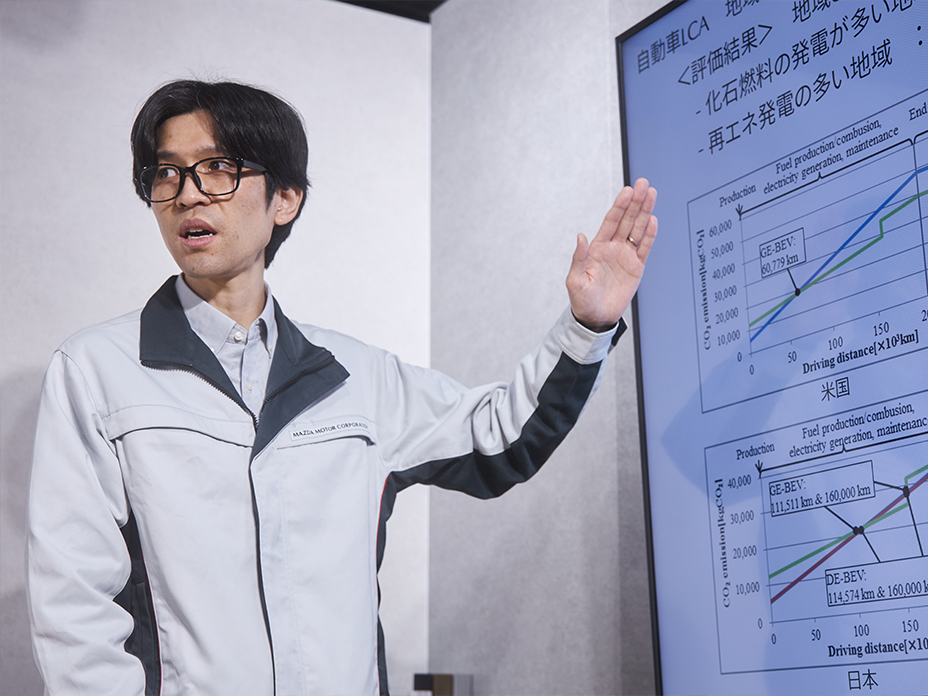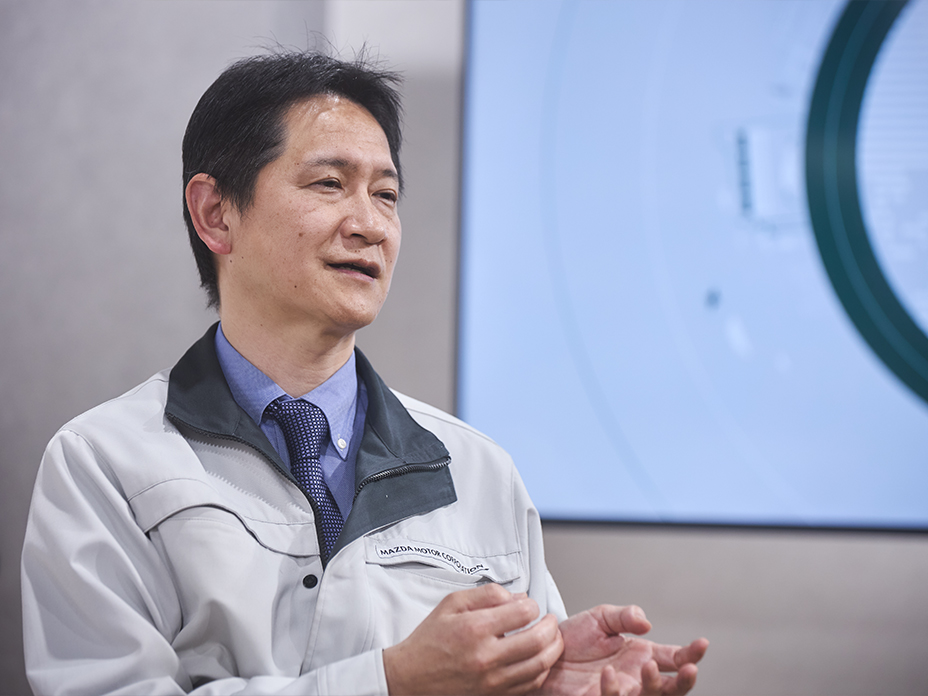今回、マツダが取り組む環境施策に切り込む青柳実可子は、コロナ禍の2020年入社。大学時代の友人がSNSに気候変動問題を投稿していたことなどをきっかけに、環境問題に関心を抱くようになりました。
入社後は、コンパクトSUV 「MX-30」の広報業務を担当。その後、サステナビリティ領域により深く関わりたいという想いから、コミュニケーション統括グループへ。現在は、マツダの環境、社会、ガバナンス(ESG)の取り組みをまとめたサステナビリティサイトの制作に携わっています。
「マツダの環境に対する取り組みや現在地、課題について、さらに解像度を高めたい」。そんな青柳の強い想いからスタートした本企画。実際に現場で施策にあたっている担当者に、マツダ社員ならではの本音で迫ります。