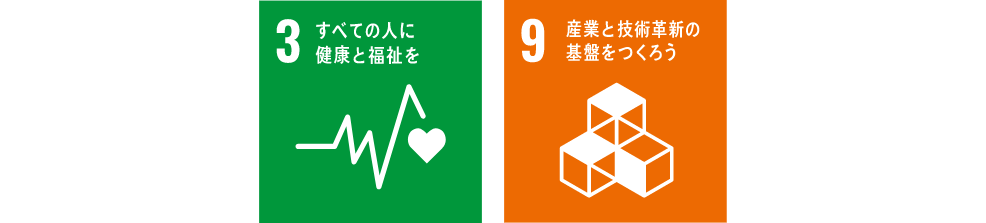世界保健機関憲章の前文によると、健康とは、「病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、全てが満たされた状態にあること」※と定義されており、well-beingという言葉を使って表現されています。
また、米国で行われた調査によると、140以上の国と地域を対象とした情緒的健康に関する調査では、「感情体験」が評価軸の一つとなっています。2006年から2022年までの期間において、ポジティブな感情体験(十分な休息・他者からの敬意・笑い・楽しい体験・興味深い学び)のスコアはほぼ横ばいの一方で、ネガティブな感情体験(体の痛み・心配・悲しみ・ストレス・怒り)のスコアは2015年以降で悪化傾向で推移しています。
今後、ポジティブな感情体験の機会を増やしていくことが、人々の情緒的健康の向上につながると考えられます。情報技術産業をはじめとした産業界の一部企業では、肉体的な健康だけでなく、精神的・社会的な健康も考慮するwell-beingの視点を技術や商品の開発に取り込む動きが始まっています。
※ Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.