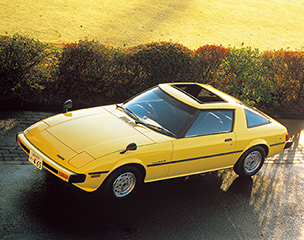3代目の〈RX-7〉は、1991年12月に発売となった。そして、このモデルから、サバンナの名称が外れた。同時に、当時の販売チャネルにちなみ、アンフィニRX-7と呼ぶことになる。
アンフィニRX-7の特徴の一つは、〈RX-7〉としてはじめて3ナンバー専用車体を採用したことである。車体寸法を2代目と比較すれば、全長、ホイールベース、全高はそれぞれ小さくなったが、全幅が広がって3ナンバーとなっている。すなわち、より低い姿勢で走行安定性を求めたスタイルであり、運動性の向上を目指したのである。
3代目の開発は、86年の秋にはじまっていた。これもまた、2代目が誕生してわずか1年後という時期である。スポーツカーの開発に、マツダがいかに時間を掛け、またその進化に対し真摯であったかがわかる。
この間、課題となったのは、スポーツカーの存在意義であった。というのも、スポーツカーが次第に上級車指向になる一方で、上級のスペシャルティカーが高性能化し、両者の違いが曖昧になってきたからだった。
同時に、それまでの大気汚染に対する排ガス規制や、オイルショックに端を発する低燃費指向とは別に、地球温暖化に対処すべく二酸化炭素の排出抑制が求められ、それは資源保護とは別の視点からの低燃費への要求であった。大排気量車の存在を疑問視する声が大きくなりだした。
そうした背景を持ちながら、次の〈RX-7〉の持つべき要素として、リアミッドシップ案、3ローターエンジン案、NAエンジン案、ターボエンジン案など、様々に意見が交わされた。また、内外のスポーツカーの試乗も幾度となく行い、開発方針を固めていくなかで生まれた言葉が、「ロータリーエンジン・ベスト・ピュア・スポーツカー」であった。