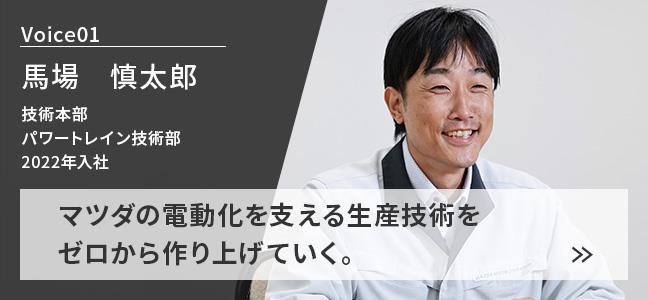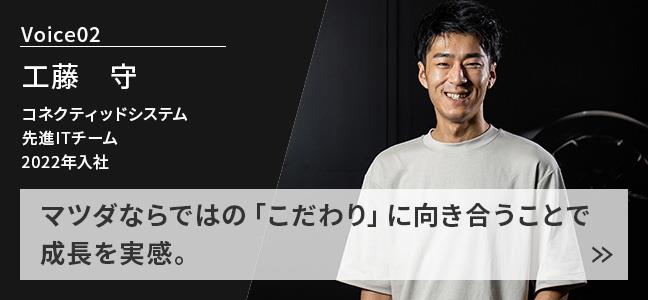人を知る 技術系
マツダの電動化を支える生産技術を
ゼロから作り上げていく。

PROFILE
馬場 慎太郎
技術本部 パワートレイン技術部
2022年入社
前職
サプライヤー(金型事業、電機/電子部品事業)の生産技術
PROFILE
馬場 慎太郎
技術本部 パワートレイン技術部
2022年入社
前職
サプライヤー(金型事業、電機/電子部品事業)の生産技術
RX-8やロードスターを乗り継ぐ熱狂的なマツダファンだった

前職は、部品メーカーでモータコアの生産技術を担当していました。新卒で入社してから4年ほど働いていましたが、OEM生産で取引先に出向したことをきっかけに、自分が携わった製品を直接世に出せる完成車メーカーで働きたいという想いが強くなり、転職を考えるようになりました。
私はRX-8やロードスター(ND)を乗り継いできた熱狂的なマツダファンなので、マツダで自分の経験を活かせる生産技術部門の募集があることを知り、すぐに応募しました。その結果、他に検討していた会社よりもスピーディーに内定をもらえたので、入社を迷う理由もありませんでした。
入社後はパワートレイン技術部にて生産技術開発領域や量産準備領域の業務を担当しています。現在マツダでは、EVシステムや構成部品の生産技術の手の内化を推進しており、私はモータ部品の生産技術開発(工法検討)やBOP(Bill Of Process)構築を狙った生産ライン/工程検討、さらには設備の仕様検討、開発部門との製品仕様検討などを任されています。また、マツダは地元サプライヤーとの共創活動にも力を入れており、私自身も地場のジョイントベンチャーとの業務に参加して電磁鋼板プレスや積層の技術開発・量産性検討を共同で進めています。
ゼロベースでラインや設備仕様を検討する醍醐味を実感

マツダの電動化への取り組みは、市場の動向を注視しつつ、限られたリソースを活用しながら慎重かつ確実に「手の内化」を進めている状況です。生産技術に関しても、投資効率を最大化させるための混流生産を念頭に置き、多品種および台数変動に対応したBOPを構想していく難しさはありますが、前職のようにクライアントから依頼された部品に合わせたラインを構築するのではなく、ゼロベースでラインや設備仕様を検討していける醍醐味を実感しています。
また、特許に関しても他社の動向を注視して進める必要があります。モータに関しては、知見がありますので、公開特許公報の内容をメンバーに向けてわかりやすく説明することもできるほか、特許内容の微妙な差異を発見してまとめるなど、自分の知識や経験が存分に役立っていると感じます。
成功も失敗も含め、さまざまなデータを蓄積していくことが重要
今後も新しい取り組みにチャレンジし続けることで、成功も失敗も含め、さまざまなデータを蓄積していくことが重要になると考えています。生産技術に関しても量産化に関しても、未来を見据えた仕様/システムを考えていく必要があります。ゼロからの立ち上げに携われるタイミングは今しかありません。将来、自分が手掛けたラインが完成し、高品質で高効率な結果が出た際には大きな喜びが得られると期待しています。また、ジョイントベンチャーでの共創も始まったばかりです。試作品の品質基準から検討しなければならない段階ではありますが、さまざまな技術・ノウハウを持った地場の方々が集まっているので、これからの進展や協業が楽しみです。
私はマツダへの入社をきっかけに、家族と共に広島に住み始めましたが、繁華街に出れば何でも揃いますし、街から海や山も近くて美味しい食べ物も多いなど、非常に住みやすい土地であると感じています。モータ部品の知識や生産技術の経験をお持ちの方であれば即戦力として活躍できると思いますので、ぜひ私たちと一緒にマツダの電動化を推進していきましょう。

※部署名・役職名は、2023年6月取材当時のものです。